高橋 卓也(滋賀県立大学)
2025年の夏はこれまで130年の間で最も暑い夏となった。2025年9月2日の朝日新聞は、「最も暑かった夏 6~8月気温平年より2.36度高く」と1面で報じた。そうした中、気候変動をテーマとしたSF(サイエンス・フィクション[科学小説]またはスペキュレイティブ・フィクション[現実世界と違った世界を想像して創作した小説])の2冊をここでは紹介したい。いずれも「水」が重要なテーマとなっている。
まず、エンミ・イタランタ著『水の継承者ノリア』(2016年刊。西村書店、1,500円+税)。著者はフィンランドの作家、コラムニスト。気候変動で大洋と大陸の形も変わってしまった世界。現在の北欧、スカンジナビア連合はニューキアン軍の占領下にある。不足している水は配給制で軍の統制下にあり、水道を勝手に引くことは禁じられている。主人公の17歳の少女ノリア・カイティオは父のような“茶人”になるための修行中である。彼女はある秘密を守るため次第に追い詰められていく。
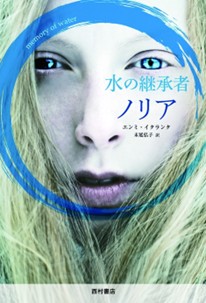
(出版社Webサイトに画像の利用許可表示あり)
森と湖の国だった北欧が、いまや乾燥地帯となってしまったという想定だ。一種のディストピア(ユートピアの逆で、社会や環境の問題が極限にまで拡大)もので、気候変動により資源、技術が失われてしまったという世界。石油は使い尽くしてプラスチックは前の時代のごみから回収してくるしかない。人々は常にのどを乾かせていて、体は自由に洗えない。外出するときには虫除け帽子を身に付けなくてはならない。
酷暑の中で読むにはきつい内容だが、救われるのは茶人がとりおこなう茶事である。救いのない乾いた世界で唯一、茶室のなかでは水をじっくりと感じることができる。先時代(気候変動前)のどこかの茶人がそうしたように、飛び石のある茶室への道にわざと葉を散らせるという心ゆかしさもある。
どこかで聞いたような「茶事」が未来社会でも続いているというのは、日本人にとってはニヤッとできる趣向であろう。何より、冷涼湿潤でありイノベーションの地である北欧が灼熱乾燥地帯へと変貌し現代社会の資源、技術が失われるという世界観を説得力をもって示しているのが作者の力業である。水が極端に不足した場合、技術では解決がつかなくなるだけではなく、社会全体が衰退してしまうというのが、理屈では説明できないが、直観的に「そうかもしれない」と私が思ったところだ。環境経済学でいう「強い持続可能性(=自然がなくなると人間社会の技術では代替しきれない)」という仮説にも思いをはせることとなった。
次は、米国のSF作家キム・スタンリー・ロビンンスン著『未来省』(2023年刊。パーソナルメディア、3,000円+税)。
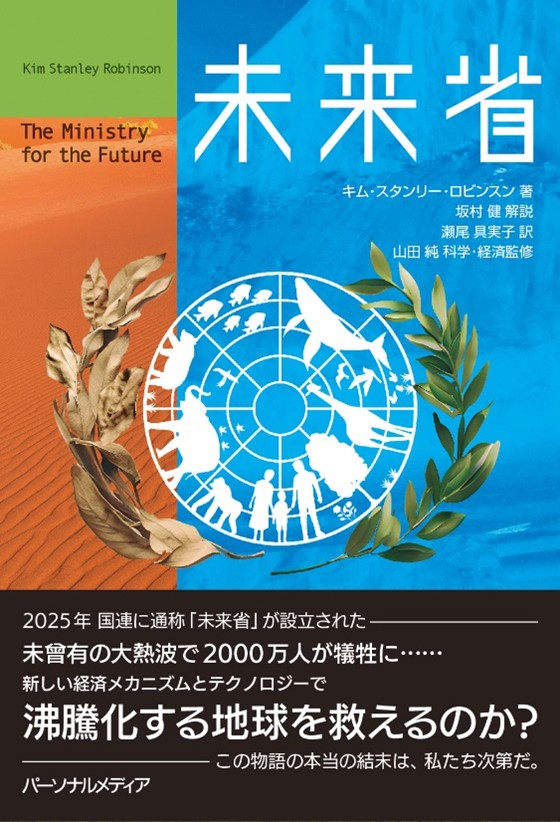
(表紙画像掲載について出版社許諾済み)
依然として進まない気候変動対策のため、国連では2025年(今年ですね)に将来世代の人類と生物を代弁する「未来省」を創設し対応しようとする。2026年、大熱波によりインドでは2000万人の死者が出る。主人公は二人、フランク・メイ―おそらくは援助関係の財団のメンバーとしてインドで大熱波を体験する男性、そしてメアリー・マーフィー―未来省の事務局長、労働組合の弁護士出身でアイルランド共和国の外務大臣も務めた45歳くらいの女性。
インドでの大熱波の描写は、酷暑の中で読むとさらにおぞましく感じられる(インドの方には縁起でもない話をすみません)。気温は42度、湖に入っても気温より高い温度で体は冷やせない。エアコン強盗が発生する。大気は煮え立つように暑い。
しかし、気候変動への緩和・対応策が数多くちりばめられているのが、この小説の面白さだ。大気中への二酸化硫黄粒子の散布による太陽光遮断、南極氷床の安定化といったジオ・エンジニアリング(地球工学)。二酸化炭素吸収と紐づけられたブロックチェーン通貨制度—カーボンコイン。さらには、対策とは言えないだろうが、気候テロリズム。そのほかにも、それらの対策の背後にある、割引率、貨幣理論、社会理論にもさらっと触れている。
監修者・解説者の坂村健氏は、取り上げられるこれら対策の多様性、文理横断的なあり方に加えて「日本の存在感のなさ」をこの小説の特徴として取り上げていた。私は気候変動問題を身体的に感じられる点をこの作品の特徴として指摘したい。インドの熱波の中での痛み、苦しさ、混乱、ヨーロッパ・アルプスでの雪と氷の世界での逃避行の寒さ、恐怖感、自然が再生されつつある(ネイチャー・ポジティブな)地球をめぐる飛行船の浮遊感、希望(この小説ではいろいろあって最後は解決へと向かいます。ネタバレですみません。)これらは自分事として気候変動を考えるきっかけとなるのではないかと感じた。
『未来省』では、最後に希望を見せてもらえるが、もっとワクワク、ドキドキ、ハラハラする未来を見たいのなら、ソーラーパンクがおすすめかもしれない。ソーラーパンクとは持続可能な社会を実現した未来を描くSFであり、かつ世界観である。私自身未読なのだが、そうらしい。技術が極限まで発達した未来を描くサイバーパンクからアイデアを得たジャンル分けのようである。とりあえずは、ウィキペディアで紹介されたイメージ図をご覧ください(図3 ソーラーパンクのイメージ)。

C.C. 4.0 An aerial view of a futuristic, sustainable Berlin
https://realutopien.info/visuals/berlin-friedrichstrasse-utopia-2048/
最後に悪乗りさせていただくと、水車パンクという世界観のSFを読んでみたい(図4:生成AIを活用して作成した「水車パンク」のイメージ図)。なぜなら、スチームパンクという分野もあるらしいからだ。スチームパンクでは、ガソリンエンジンなどの内燃機関ではなくイギリス・ビクトリア朝時代の蒸気機関が社会の主要な動力であり続けた世界を描く(図5:ウィキペディア「スチームパンク」に掲載されている乗り物のイメージ図)。ジブリ制作のアニメでいうと、「ハウルの動く城」「天空の城ラピュタ」がそうらしい。水車パンクでは、水車が社会の動力であり続けた世界を描く。長編だと破綻をきたす設定かもしれないが、短編なら何とかならないか。前回の随想で地元の水車について書いたのでこのようなことを思い付いてしまった(明治の彦根に水車が回る―「青天を衝け」と彦根製糸場)。ところで、すでに水車パンク作品は存在するのかもしれない。もしご存知でしたらお知らせください。

(OpenAI Soraを使用して作成)

Ann Larie Valentine – Flickr: The Neverwas Haul, CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32128635